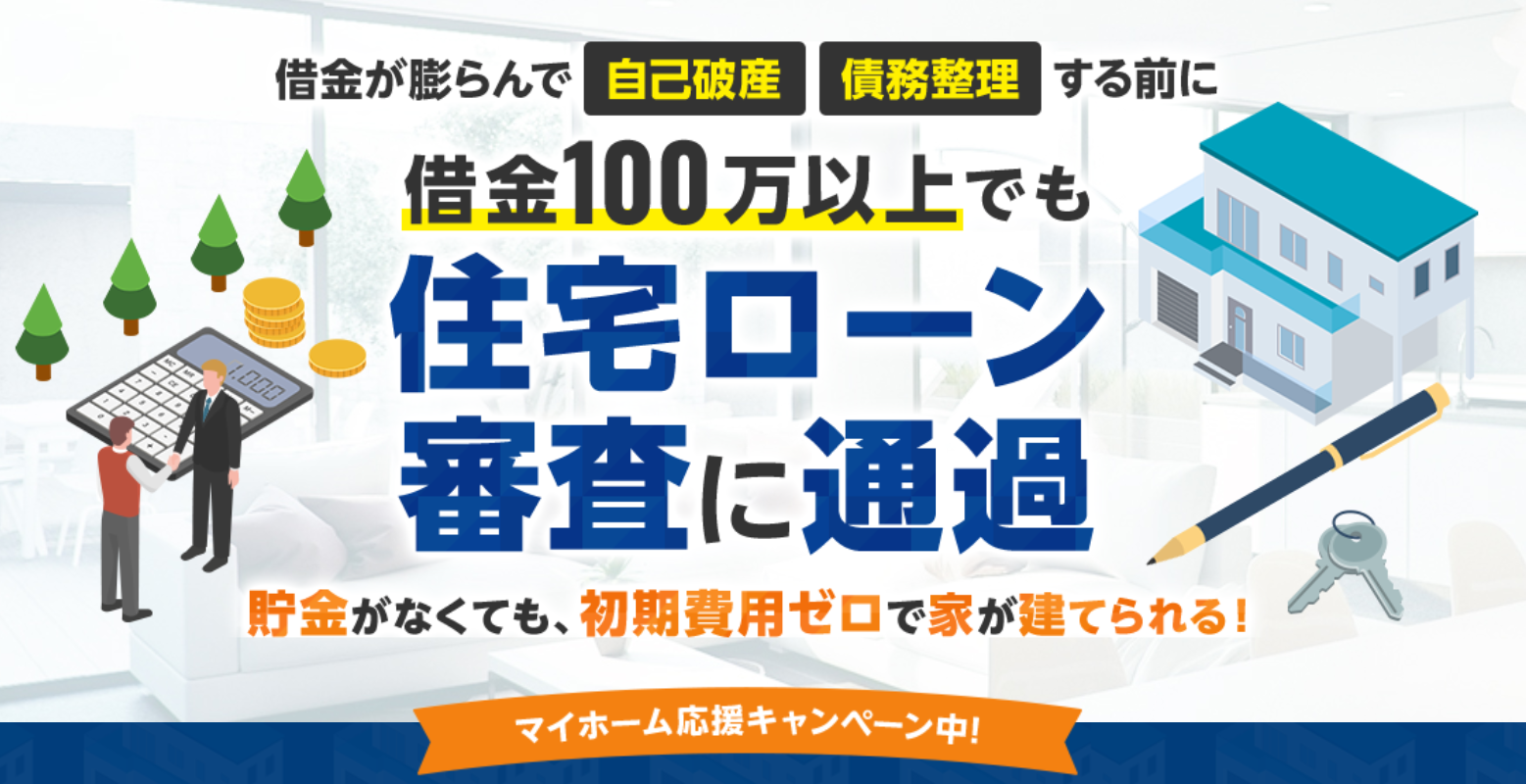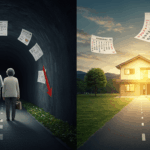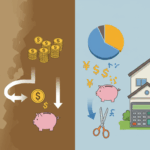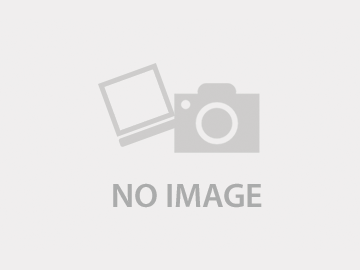2024年のマイナス金利解除に続き、2025年に入り日銀が追加利上げに踏み切ったことで、金利は本格的な上昇局面に入りました。この状況下で、5年ルール・125%ルールを正しく理解していないと、数年後に「こんなはずではなかった」と後悔することになります。
本記事では、住宅ローンの専門家として、これらのルールの本当の意味、そして金利上昇局面であなたが「今すぐ取るべき行動」を徹底的に解説します。
5年ルール・125%ルールとは?基本の仕組みを理解する

この2つのルールは、変動金利の「元利均等返済」を選んだ場合に適用される、家計の急変を防ぐための仕組みです。
5年ルールの基本的な仕組み
5年ルールとは、変動金利型住宅ローンにおいて、適用金利が変動しても(通常は半年ごと)、毎月の返済額は5年間変わらない(据え置き)という仕組みです。
5年ルールの重要ポイント
- 金利の見直し:半年ごとに実施
- 返済額の見直し:5年ごとに実施
- 適用対象:元利均等返済の変動金利のみ(※一部銀行を除く)
125%ルールの基本的な仕組み
125%ルールは、5年ごとの返済額見直し時に、新しい返済額がそれまでの返済額の125%(1.25倍)を超えないようにする仕組みです。
例えば、現在の毎月返済額が10万円の場合、5年後の見直し時には、どれだけ金利が上がっていても最大12.5万円までしか上がりません。
なぜこのようなルールが存在するのか?
これらのルールは、金利が急上昇した場合でも、家計への急激な負担増を防ぐための「激変緩和措置」です。しかし、この「優しさ」こそが、金利上昇局面で最大の落とし穴となります。
9割の人が勘違い!5年ルールの本当の意味

❌ よくある誤解1:「5年間は金利が上がらない」
これは完全な誤解です。金利は半年ごとに見直されており、市場金利が上昇すれば、あなたの住宅ローン金利も上昇します。5年ルールで変わらないのは「毎月の返済額(=口座から引き落とされる額)」だけで、「金利」は変動しているのです。
❌ よくある誤解2:「5年間は利息が増えない」
これも大きな間違いです。金利が上昇すれば、その時点から利息の支払い額は増えています。では、返済額が変わらないのに利息が増えるとどうなるのでしょうか?
衝撃の事実:返済額の内訳が激変する
金利が上昇すると、毎月の返済額は変わらなくても、その内訳(元金と利息の割合)が変化します。
- 利息の割合が増加
- 元金返済の割合が減少
- 結果:元金の減りが恐ろしく遅くなる
具体例で理解する返済額の内訳変化
借入額3,000万円、当初金利0.5%、35年返済(毎月返済額:77,875円)の場合:
| 状況 | 毎月返済額 | 利息部分 | 元金返済部分 |
|---|---|---|---|
| 当初(金利0.5%) | 77,875円 | 12,500円 | 65,375円 |
| 2年後(金利1.5%に上昇) | 77,875円(変わらず) | 37,500円 (3倍!) | 40,375円 (激減) |
ご覧の通り、返済額は同じでも、払っている利息が3倍になり、元金返済が月2.5万円も減っています。5年間これが続くと、元金が約150万円(2.5万円×60ヶ月)も減らない計算になり、将来の総返済額が膨れ上がります。
最悪のシナリオ「未払利息」という落とし穴

5年ルールの最大の恐怖は、金利がさらに上昇した場合に発生する「未払利息」です。
未払利息とは何か?
未払利息とは、金利が大幅に上昇した結果、毎月の返済額(例:77,875円)よりも、その月に払うべき利息額(例:80,000円)の方が大きくなってしまう状態です。
危険な状況:元金が1円も減らない
毎月の返済額が利息すら払いきれないため、以下の事態が発生します。
- 元金は1円も減らない。
- 支払いきれなかった利息(この例では2,125円)は「未払利息」として累積していく。
- この未払利息には、原則利息はかかりません(銀行による)が、借金が借金を呼ぶ状態です。
未払利息が発生したらどうなる?
このルールは一時しのぎに過ぎません。5年ルール・125%ルールで先送りした元金や未払利息は、免除されるわけでは決してありません。
最終的には、返済期間の最後に「残額を一括でお支払いください」と、数百万円単位の一括返済を求められるリスクがあります。これが「変動金利地獄」と呼ばれる状態です。
あなたのローンは大丈夫?金利上昇リスクを今すぐ「無料診断」

「未払利息」や「元金が減らない」という話を聞いて、ご自身の住宅ローンが不安になった方も多いのではないでしょうか。
「私のローンはあと何年で金利が何%になったら危険なの?」
「このまま今の変動金利を続けていいの?」
この不安を解消するために、まず「あなたのローンの現在地」を客観的に知ることが不可欠です。
しかし、自分で複雑なシミュレーションをするのはほぼ不可能です。そこでお勧めしたいのが、AIがあなたのローン状況を無料で診断してくれる「モゲチェック」です。
なぜ「モゲチェック」が必要なのか?
モゲチェックは、現在のローン情報を入力するだけで、以下の2点を完全無料で診断してくれます。
- あなたのローンの「借り換えメリット額」
AIが全国120以上の銀行から、今より有利な(=金利が低い)ローンを瞬時に比較・提案。金利上昇リスクをリセットできます。 - 将来の金利上昇リスク診断
このまま金利が上がった場合、あなたの返済額がどうなるかをシミュレーションできます。
「不安なまま放置」することが最大のリスクです。まずは専門のAIを使い、あなたのローンが安全圏にあるのか、それとも今すぐ対策(借り換え)が必要なのかを無料で確認しましょう。
メリット・デメリットを冷静に比較
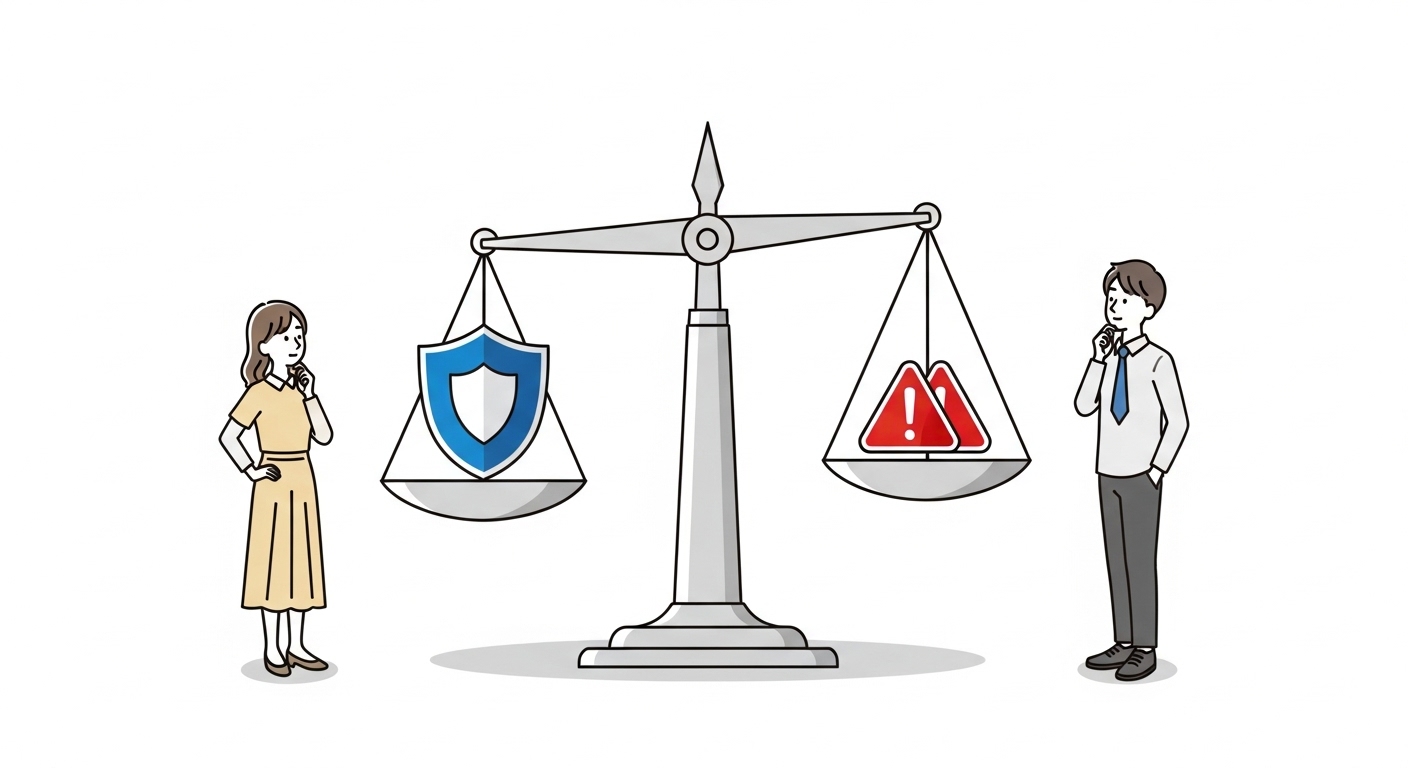
5年ルール・125%ルールのメリット
- ✅ 家計の急激な変化を防げる(最大のメリット)
金利が上昇しても5年間は返済額が変わらないため、家計管理がしやすい。特に子育て世帯など、数年間は支出を増やせない家庭には助かります。 - ✅ 返済計画の見直し時間を確保できる
5年の猶予期間があれば、収入アップや繰り上げ返済の準備、借り換えの検討など、対策を講じる時間を稼げます。
5年ルール・125%ルールのデメリット
- ❌ 元金の返済が遅れる(最大のデメリット)
前述の通り、金利上昇時は利息ばかりを払い、元金が減りません。結果、総返済額が増加します。 - ❌ 未払利息が発生する可能性
金利が想定以上に高騰すると、元金ゼロどころか利息すら払いきれない事態になります。 - ❌ 問題の先送りでしかない
これらのルールは一時的な緩和措置であり、金利上昇による負担増という根本的な問題を解決するものではありません。
5年ルールがない銀行一覧【2025年11月版】
実は、すべての銀行がこのルールを採用しているわけではありません。以下のネット銀行などは、5年ルール・125%ルールを「採用していません」。
5年ルール・125%ルールがない主要銀行
| 銀行名 | 特徴 | 2025年11月変動金利(例) |
|---|---|---|
| SBI新生銀行 | 5年ルールなし。金利下降時にすぐ返済額が減る。 | 0.290%~ |
| ソニー銀行 | 5年ルールなし。金利上昇時はすぐ返済額に反映。 | 0.397%~ |
| PayPay銀行 | 5年ルールなし。トップクラスの低金利。 | 0.299%~ |
※金利は執筆時点の目安です。最新情報は公式サイトでご確認ください。
5年ルールがない銀行のメリット・デメリット
- メリット:金利下降時の恩恵をすぐに受けられる。金利が上がっても元金は着実に減っていくため、未払利息が発生しない。
- デメリット:金利上昇時にすぐに返済額が増える。125%の上限もないため、家計管理が難しくなる。
2025年の金利動向と今すぐできる3つの対策

2025年1月の日銀追加利上げを受け、短期プライムレートは上昇傾向にあります。2025年後半~2026年にかけて、さらなる利上げ(政策金利1%程度まで)も市場では織り込まれ始めています。
変動金利は0.3%台の低水準を維持していますが、これは銀行間の熾烈な競争によるもの。この「異常な低金利」が永遠に続く保証はどこにもありません。
対策1:家計の見直し(守りの対策)
5年ルールがある場合でも、5年後には確実に返済額が増えます。今のうちから「現在の返済額の125%」で生活できるか試算し、無駄な支出(サブスク、保険など)を削減しましょう。
対策2:繰り上げ返済の準備(守りの対策)
元金を減らせば、金利上昇時の利息負担を軽減できます。ただし、住宅ローン控除(減税)期間中は、控除額と金利を比較して慎重に判断しましょう。
対策3:【最重要】固定金利への借り換え(攻めの対策)
金利上昇が本格化する前に、より金利の低い変動金利、または安心できる固定金利に「借り換える」ことが、最も強力な対策です。
「でも、借り換えって面倒そう…」「手数料もかかるし…」「私でも審査通るの?」
その悩み、すべて「モゲチェック」が解決してくれます。AIが全国120以上の銀行から、あなたにとって最も有利な借り換え先を提案し、面倒な手続きもサポートしてくれます。まずは「借り換えたら、あといくら得するか」を診断するだけでも価値があります。

よくある質問と回答
(Q&Aセクションは元の記事内容を維持します。情報の正確性に問題はありません。)
Q1. 5年ルールは全ての変動金利に適用されますか?
A. いいえ。元利均等返済のみが対象で、元金均等返済には適用されません。また、SBI新生銀行など一部の銀行では元利均等返済でも適用しません。
Q2. 125%ルールで返済額が抑えられた分はどうなりますか?
A. 免除されるわけではなく、後から必ず支払う必要があります。返済期間の延長や、最終返済時の一括支払いなどで清算することになります。
Q3. 未払利息が発生する可能性は本当にありますか?
A. 現在の低金利環境では可能性は低いですが、金利が4%を超えるような状況になれば、発生する可能性があります。バブル期には実際に多くの人が未払利息に苦しみました。
Q4. 5年ルールがない銀行は危険ですか?
A. 必ずしも危険ではありません。むしろ、金利変動に透明性があり、元金が確実に減るというメリットもあります。重要なのは、自分の収入や家計状況に合った選択をすることです。
Q5. 今から固定金利に変更すべきですか?
A. 一概には言えません。だからこそ、「モゲチェック」のような比較サービスで、ご自身の状況に合わせた最適なプランを診断する必要があります。
まとめ:不安なまま放置が最大のリスク。今すぐ「専門家」に相談を

5年ルール・125%ルールは、金利上昇時の「痛み止め」でしかありません。病気の「根本治療」にはならないのです。
2025年、金利が本格的な上昇局面に入った今、変動金利を組んでいる(組もうとしている)あなたが取るべき行動は、「不安なまま放置しない」こと、ただ一つです。
大切なのは、以下の3つです:
- 正しい知識を持つこと(5年ルールは金利を固定しないと知る)
- 自分の状況を把握すること(今のローンが危険か診断する)
- 備えをすること(金利上昇に対応できる借り換えや家計を作る)
「どう備えたらいいか分からない」「借り換えと言われても、自分一人では判断できない」
もしそう感じるなら、中立的な立場のプロ(ファイナンシャルプランナー)に相談することを強くお勧めします。
「家づくり相談所」では、住宅ローンに強いFPが、あなたの現在のローン状況や家計を無料で診断。「このまま変動で大丈夫か」「借り換えるならいつが良いか」「老後まで含めたキャッシュフローは持つのか」を、あなた専用の計画表で分かりやすく示してくれます。
銀行の窓口では「自社の商品」しか勧められませんが、中立的なFPなら、あなたにとって本当にベストな選択肢を一緒に考えてくれます。金利上昇が本格化する前に、ぜひ一度「家計の健康診断」を受けてみてください。