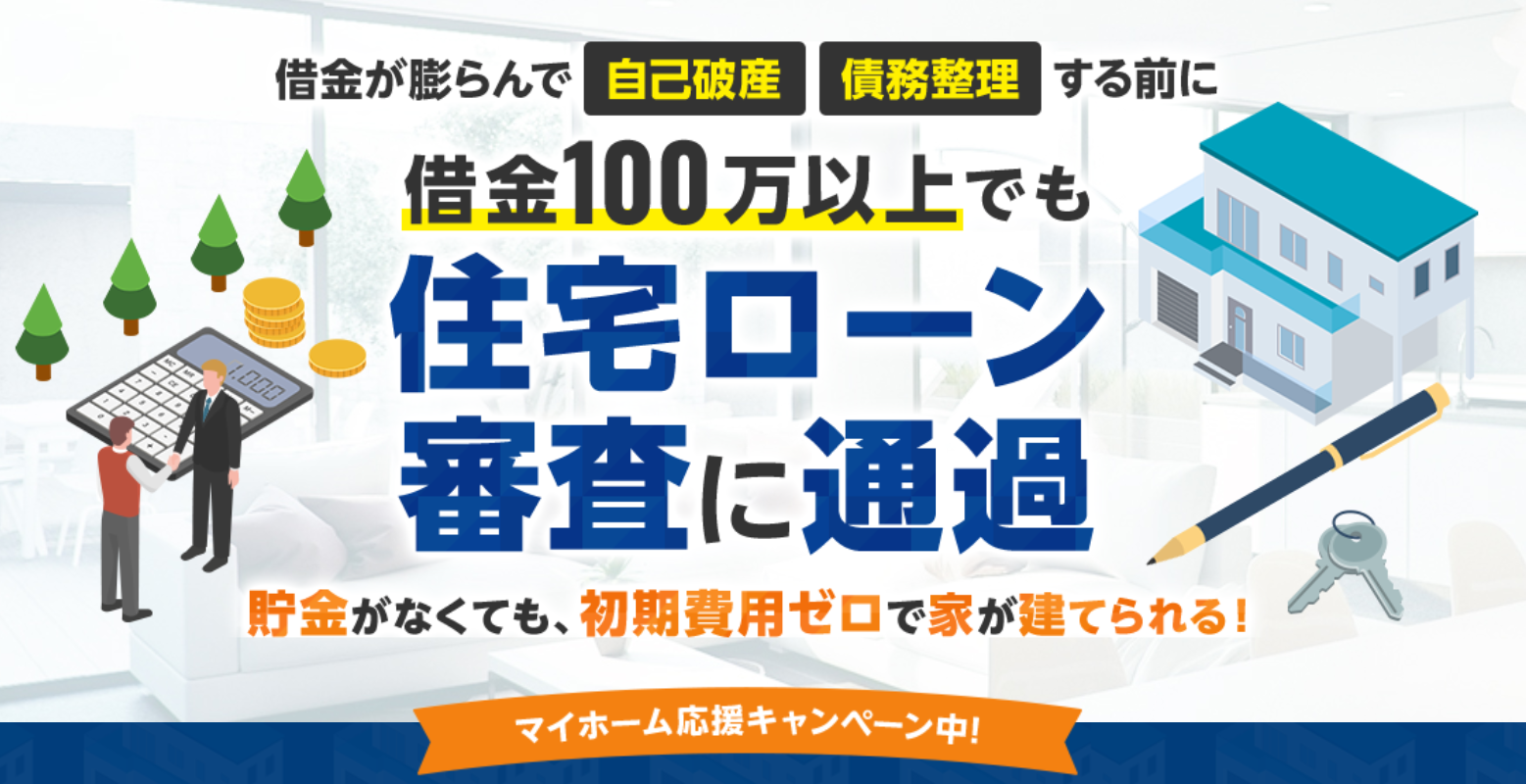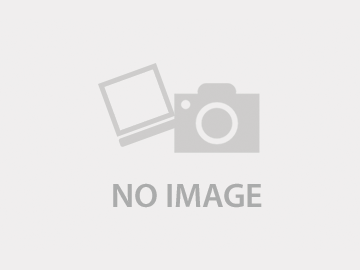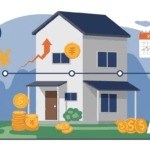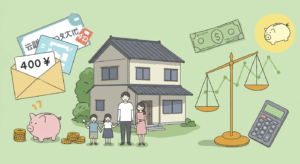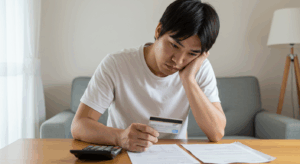相続で揉めている不動産が1,000万円の資金に変わる!共有持分融資の衝撃
「兄弟で相続した実家、自分の持分だけでお金を借りたい」「離婚協議中の共有名義マンション、相手の同意なしに資金調達したい」実は、共有持分だけを担保に、他の共有者の同意なしで融資を受けられる方法があります。相続や離婚で困っている方に、共有持分専門の不動産担保ローンという解決策を徹底解説します。
なぜ共有持分の不動産は「負動産」になるのか?
共有持分が抱える5つの問題
共有持分所有者の悩みランキング
-
売却できない(82%)
- 共有者全員の同意が必要
- 一人でも反対すれば売却不可
- 市場価値の1/3以下でしか売れない
-
活用できない(75%)
- 賃貸に出すにも全員同意が必要
- リフォームも勝手にできない
- 固定資産税だけ払い続ける
-
融資が受けられない(93%)
- 銀行は共有持分を担保として認めない
- 「完全所有権にしてから」と門前払い
-
相続でさらに複雑化(68%)
- 代が変わるごとに共有者増加
- 連絡先不明の共有者が発生
-
精神的ストレス(89%)
- 共有者との関係悪化
- 解決の糸口が見えない
2025年の相続不動産の実態
- 相続不動産の約40%が共有名義
- 共有持分のまま10年以上放置:全体の65%
- 共有者間でトラブル発生:78%
- 固定資産税の負担で揉める:45%
- 空き家化して管理放棄:32%
共有持分でも融資可能!知られざる資金調達法
なぜ一般の金融機関は共有持分を嫌うのか?
銀行が共有持分融資を避ける理由
-
法的リスク
- 他の共有者からのクレーム可能性
- 競売時の換価が困難
- 法的手続きの複雑さ
-
評価の困難さ
- 持分のみの市場価値算定が困難
- 買い手が限定的で流動性が低い
-
回収リスク
- 万が一の際の処分が困難
- 共有物分割請求の手間とコスト
結果:99%の金融機関が融資不可
共有持分専門ノンバンクが融資できる理由
- 専門的な評価ノウハウ 20年以上の共有持分取扱実績 独自の評価基準と査定方法
- 不動産事業との連携 最悪の場合でも買取可能 共有持分の市場を熟知
- 法務チームの存在 司法書士・弁護士との連携 トラブル対応のノウハウ蓄積
- リスク管理体制 適切な融資率設定(40-50%) 綿密な権利関係調査
実例公開!共有持分で資金調達に成功した5つのケース
ケース1:相続で揉めている実家(持分1/3)で事業資金調達
Aさん(45歳・飲食店経営)の事例
【状況】
- 実家(評価額3,000万円)を3兄弟で相続
- 長男は売却希望、次男は維持希望で対立
- Aさん(三男)は事業資金500万円が必要
【解決】
- 持分1/3(評価額1,000万円)を担保に融資申込
- 他の兄弟への連絡・同意一切不要
- 融資額:500万円(金利5.8%)
- 申込から3日で融資実行
兄弟間のトラブルを避けながら資金調達成功
ケース2:離婚協議中の共有マンションで生活資金確保
- 状況 マンション(評価額4,000万円)を夫婦で1/2ずつ所有 離婚協議が長期化、生活費に困窮
- 問題点 夫が売却を拒否 住宅ローン残債1,500万円
- 解決策 妻の持分1/2で300万円融資 当面の生活資金と弁護士費用を確保 財産分与決定後に完済予定
ケース3:親族共有の土地で老人ホーム入居資金
Bさん(72歳・年金生活)の事例
【背景】 祖父から相続した土地をいとこ4人で共有 自分の持分は1/4(評価額800万円相当) 老人ホーム入居一時金600万円が必要
【結果】 ・持分1/4のみで400万円融資獲得 ・年金から月5万円返済 ・他の共有者には一切連絡せず ・安心して老後生活をスタート
ケース4:共有アパートの持分でリフォーム資金
- 父から相続したアパート(1/2持分)
- 兄が残り1/2を所有も音信不通
- 老朽化で入居率低下、リフォーム必要
- 持分担保で800万円調達
- リフォーム後、家賃収入で返済
ケース5:相続税納税資金を共有持分で調達
緊急の納税資金調達に成功
相続税納付期限まで残り1ヶ月 現金資産なし、不動産のみ相続 共有持分(評価額2,000万円)で納税資金1,000万円調達 延納利子税(年14.6%)より低金利(6.5%)で解決
共有持分の評価方法と融資可能額の目安
持分評価の計算方法
共有持分の融資可能額シミュレーション
【基本計算式】 不動産全体の評価額 × 持分割合 × 融資率 = 融資可能額
【具体例】 評価額3,000万円の実家、持分1/3の場合 3,000万円 × 1/3 × 50% = 500万円
【融資率の目安】 ・都心部マンション:50-60% ・郊外戸建て:40-50% ・地方不動産:30-40% ・築古物件:30-40%
エリア別の融資条件
- 東京23区 最も有利な条件 融資率:最大60% 金利:3.8%〜
- 東京都下・神奈川県 標準的な条件 融資率:最大50% 金利:4.5%〜
- 埼玉県・千葉県 エリアにより差あり 融資率:最大45% 金利:5.0%〜
共有持分融資のメリット・デメリット完全解説
5つの大きなメリット
共有持分融資だからこそのメリット
-
他の共有者の同意不要 トラブル回避しながら資金調達 プライバシー保護
-
スピード融資 権利関係の確認のみで審査可能 最短2日で融資実行
-
売却より有利 持分売却は市場価格の30%程度 融資なら50%の資金調達可能
-
将来の選択肢を残せる 完済後は元の状態に戻る 相続や売却の可能性を維持
-
固定資産税の支払い原資確保 税金滞納リスクを回避
注意すべきデメリット
- 金利が若干高め:通常の不動産担保より1-2%高い
- 融資率が低い:完全所有権の70%に対し40-50%
- 将来の売却時に抵当権解除が必要
- 他の共有者に知られる可能性:登記簿で確認可能
- 返済不能時のリスク:持分を失う可能性
共有持分融資の審査基準と必要書類
審査で重視される5つのポイント
- 権利関係の明確性 登記簿謄本で持分割合を確認 権利に瑕疵がないか
- 不動産の立地・築年数 一都三県が有利 築30年以内が理想
- 返済能力 年収の証明 他の借入状況
- 資金使途 明確な使い道 返済計画の妥当性
- 共有者との関係性 トラブルの有無 将来的なリスク評価
最低限必要な書類
共有持分融資の必要書類
【絶対必要】 □ 本人確認書類(運転免許証等) □ 登記簿謄本(3ヶ月以内) □ 固定資産税納税通知書 □ 収入証明書
【あれば有利】 □ 不動産の図面 □ 共有者一覧表 □ 遺産分割協議書(相続の場合) □ 離婚協議書案(離婚の場合)
通常の融資より書類は少なめ
よくある質問:共有持分融資の疑問を解決
Q1:本当に他の共有者にバレない?
Q2:共有者が反対したらどうなる?
Q3:将来、共有物分割請求されたら?
Q4:相続で共有者が増えたら?
共有持分の問題を根本解決する3つの選択肢
選択肢1:共有持分を買い取ってもらう
- 他の共有者に買取を打診
- 融資資金を交渉材料に
- 適正価格での売却を実現
- 完全に縁を切れる
選択肢2:共有物分割請求を行う
法的手続きによる解決
- 協議による分割
- 調停による分割
- 裁判による分割
融資で得た資金を弁護士費用に充当 1-2年で解決を目指す
選択肢3:現状維持しながら有効活用
- 融資資金で収益物件購入
- 家賃収入で返済
- 資産を増やしながら問題先送り
- 将来の交渉力を高める
2025年の法改正で共有持分はどうなる?
所有者不明土地問題への対応
2023年4月施行の民法改正の影響
【改正のポイント】 ・共有物の管理行為が過半数で可能に ・所在不明共有者の持分取得制度創設 ・共有物分割請求の要件緩和
【共有持分所有者への影響】 ✓ 共有物の活用がしやすくなる ✓ 問題解決の選択肢が増える ✓ 持分の価値が上がる可能性
今が共有持分活用の好機
まとめ:共有持分を「負動産」から「資産」に変える
共有持分融資が最適な人
✓ 相続で共有名義になった不動産がある ✓ 離婚協議中で共有名義の不動産がある ✓ 他の共有者と連絡が取れない・関係が悪い ✓ 急ぎで資金が必要 ✓ 売却より融資で解決したい ✓ 将来の選択肢を残したい
該当する方は、専門ノンバンクの無料査定がおすすめ
共有持分は確かに制約が多い資産ですが、適切に活用すれば十分な資金調達が可能です。特に、相続や離婚でお困りの方にとって、共有持分融資は問題解決の第一歩となるでしょう。
共有持分専門!20億円以上の融資実績
一都三県の共有持分なら丸の内AMS
【丸の内AMS】共有持分融資の強み
-
圧倒的な実績 共有持分融資実績20億円以上 取扱件数500件以上
-
他の共有者への連絡不要 完全秘密厳守 トラブル回避のノウハウ
-
スピード審査 最短当日回答 融資まで最短2日
-
柔軟な審査基準 年齢不問 他社で断られた案件も相談可
-
適正な評価 不動産事業のノウハウ活用 一都三県特化で地域精通
-
安心の実績 創業20年以上 金融庁登録済み
融資額:500万円〜5億円 金利:3.8%〜
共有持分でお悩みの方、まずは無料査定であなたの持分の価値を確認してみませんか?他の共有者に知られることなく、最短当日で融資可能額が分かります。相続や離婚の問題解決の第一歩を、今すぐ踏み出しましょう。█