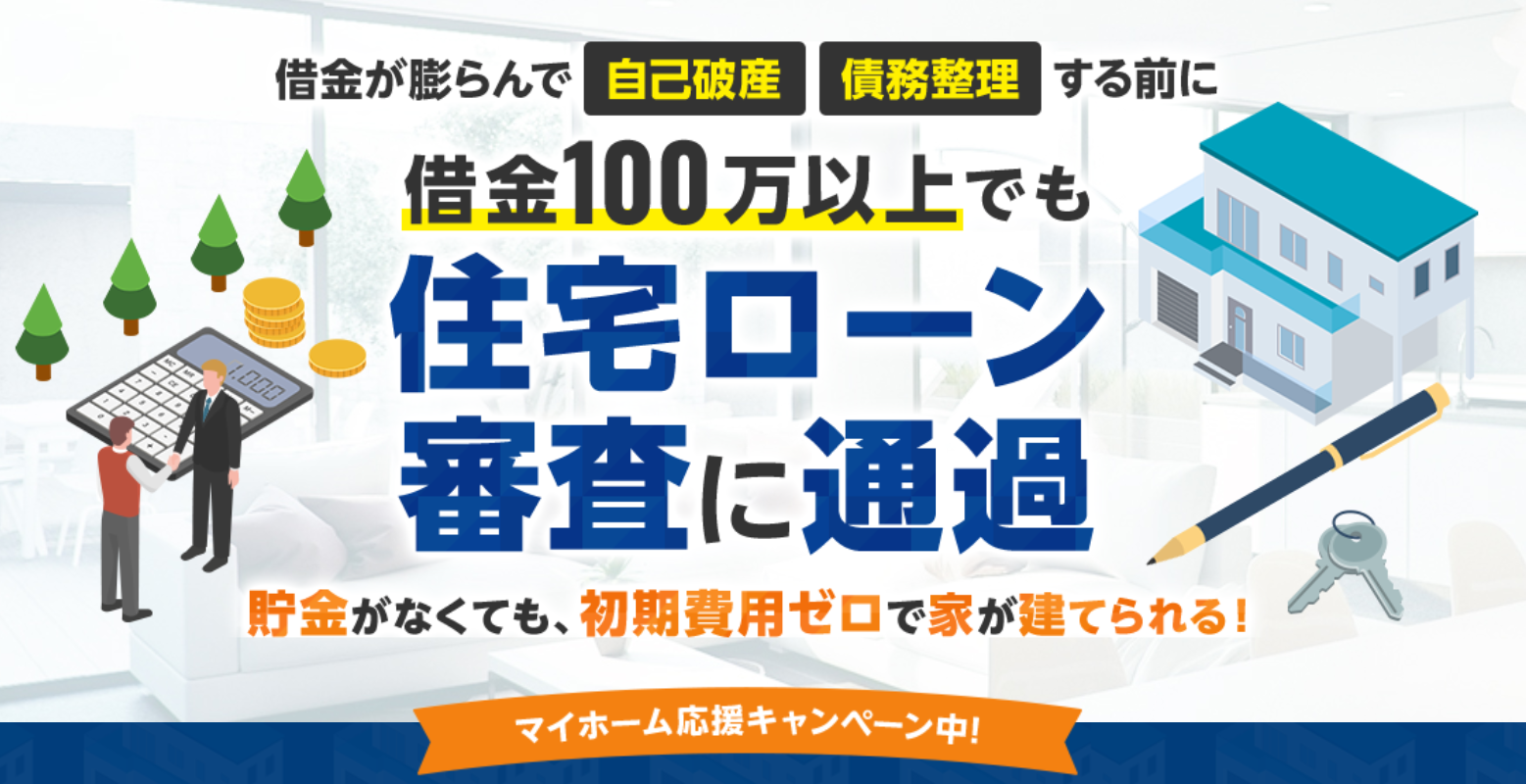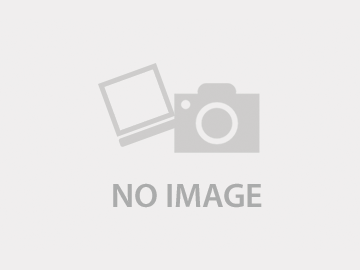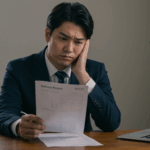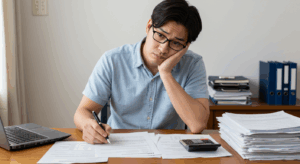土地選びで用途地域を知らずに失敗…そんな後悔、したくないですよね
「隣に高層マンションが建って、日当たりが最悪に…」
「静かな住宅街だと思ったら、工場の騒音がうるさい」
「店舗併用住宅を建てたかったのに、建てられない土地だった」
そんな失敗、したくないですよね?
実は、土地購入者の約42%が「用途地域を知らずに土地を買った」と答えています。そして、「土地選びで後悔したこと」の上位に「用途地域を調べなかった」が入っています。
「用途地域」という言葉を聞いたことがありますか?これを知らずに土地を買うと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
でも、安心してください。用途地域を理解して土地を選べば、失敗は防げます。
この記事では、住宅業界で15年以上、2,500組以上の家づくりをサポートしてきた経験から、用途地域を知らずに失敗した人の実例と、用途地域を理解して成功した人の実例をお伝えします。
- 用途地域を知らずに失敗した4家族のリアルな実例
- 用途地域を理解して成功した4家族の実例
- 用途地域とは何か?13種類の特徴
- 土地選びで失敗しない7つのチェックポイント
- 用途地域の調べ方
【実例】用途地域を知らずに失敗した4家族

まずは、用途地域を知らずに土地を買って失敗した方の実例からお伝えします。
ケース1:隣に高層マンションが建って日当たり最悪(田中家・家族4人)
購入した土地:近隣商業地域
問題:購入2年後、隣の空き地に10階建てマンションが建設
結果:日当たりが最悪に、リビングが常に暗い
購入時の状況:
閑静な住宅街に見えた。
隣は空き地で日当たり良好。
「ここなら間違いない」と即決で購入。
2年後の現実:
隣の空き地に10階建てのマンションが建設。
南側が完全に塞がれ、リビングが真っ暗。
昼間でも照明が必要。
洗濯物も乾かない。
田中さんの後悔:
「用途地域を全く確認していませんでした。『近隣商業地域』は高い建物が建てられる地域だと、後から知りました。不動産屋も教えてくれなかった。第一種低層住居専用地域なら、高い建物は建たなかったのに…」
失敗の理由:
- 用途地域を確認しなかった
- 「今の状態」だけで判断した
- 「将来何が建つか」を考えなかった
- 不動産屋の説明を鵜呑みにした
ケース2:工場の騒音に悩まされている(佐藤家・夫婦2人)
購入した土地:準工業地域
問題:購入1年後、隣に小規模工場が建設
結果:騒音と振動で生活できない
購入時の状況:
価格が安く、駅も近い。
周りは住宅が多く、「住宅街」に見えた。
「お得な土地を見つけた」と喜んで購入。
1年後の現実:
隣の空き地に金属加工の工場が建設。
朝7時から夜9時まで機械の音と振動。
週末も稼働しており、休まらない。
窓を開けられない。
佐藤さんの後悔:
「『準工業地域』だと知っていたら、絶対に買いませんでした。この地域は工場が建てられるんです。不動産屋は『住宅も多いですよ』としか言わなかった。売却も考えましたが、工場の隣なので買い手が付きません」
失敗の理由:
- 準工業地域の意味を知らなかった
- 「住宅が多い」だけで判断した
- 「工場が建つ可能性」を考えなかった
- 価格の安さに飛びついた
ケース3:店舗併用住宅が建てられなかった(山田家・夫婦2人)
購入した土地:第一種低層住居専用地域
問題:店舗併用住宅を建てようとしたが、建築不可
結果:夢だったカフェ併用住宅を諦めた
購入時の状況:
「将来カフェを開きたい」という夢。
静かで環境が良い土地を購入。
「ここでカフェをやる」と計画。
購入後の現実:
設計士に相談したら「この土地では店舗は建てられない」と言われた。
第一種低層住居専用地域は、店舗がほぼ禁止。
夢だったカフェ併用住宅を諦めることに。
山田さんの後悔:
「用途地域によって建てられる建物が制限されることを知りませんでした。第一種低層住居専用地域は、住宅専用の地域。店舗はほぼ建てられません。近隣商業地域や準住居地域なら建てられたのに…」
失敗の理由:
- 用途地域による建築制限を知らなかった
- 土地購入前に設計士に相談しなかった
- 「環境が良い」だけで選んだ
- 将来の用途を考えなかった
ケース4:再建築できない土地だった(高橋家・家族3人)
購入した土地:市街化調整区域
問題:建て替えができない
結果:将来建て替えられない、資産価値ゼロ
購入時の状況:
広い土地が格安で売られていた。
「お買い得」と思って購入。
古家付きだが、「建て替えればいい」と考えていた。
購入後の現実:
建て替えを検討したら「市街化調整区域なので再建築不可」と判明。
リフォームはできるが、建て替えは原則不可。
将来売却もほぼ不可能。
資産価値がない土地を買ってしまった。
高橋さんの後悔:
「『市街化調整区域』の意味を全く知りませんでした。この地域は原則として建物を建てられない地域。既存の建物はあっても、建て替えはできないんです。安かった理由がやっと分かりました…」
失敗の理由:
- 市街化調整区域の意味を知らなかった
- 「格安」に飛びついた
- 再建築の可否を確認しなかった
- 専門家に相談しなかった
【実例】用途地域を理解して成功した4家族

次に、用途地域を理解して土地を選び、成功している方の実例をご紹介します。
ケース1:第一種低層住居専用地域で静かな住環境を実現(鈴木家・家族4人)
購入した土地:第一種低層住居専用地域
特徴:建物の高さ制限あり(10mまたは12m)
結果:日当たり良好、静かな住環境を維持
購入時の判断:
「将来も変わらない住環境が欲しい」と考え、用途地域を徹底調査。
第一種低層住居専用地域を選択。
やや価格は高いが、「安心料」と考えた。
5年後の現実:
周りは2階建ての戸建てのみ。
高い建物が建つ心配がない。
静かで、子育てに最適。
資産価値も維持。
鈴木さんの成功の秘訣:
「『第一種低層住居専用地域』は、最も住環境が守られる地域です。高さ制限があるので、将来も日当たりが確保されます。価格は高いですが、後悔しない選択でした」
成功の理由:
- 用途地域を徹底的に調べた
- 「将来も変わらない」を最優先にした
- 高さ制限のメリットを理解していた
- 長期的な視点で判断した
ケース2:準住居地域で店舗併用住宅を実現(中村家・夫婦2人)
購入した土地:準住居地域
特徴:店舗も住宅も建てられる
結果:1階カフェ、2階住居の理想を実現
購入時の判断:
「カフェ併用住宅を建てたい」という明確な目的。
用途地域を調べ、準住居地域または近隣商業地域を探した。
「店舗可」の地域を選択。
3年後の現実:
1階で念願のカフェを営業。
2階は住居として快適。
「住環境と仕事を両立できた」
中村さんの成功の秘訣:
「『準住居地域』は、住宅も店舗も建てられる地域です。第一種低層住居専用地域では店舗は建てられないので、用途地域を調べて正解でした」
成功の理由:
- 目的に合った用途地域を選んだ
- 事前に建築制限を調べた
- 設計士にも相談した
- 「店舗可」の地域を探した
ケース3:用途地域から将来の環境変化を予測(木村家・家族3人)
購入した土地:第一種中高層住居専用地域
特徴:マンションも建てられるが、商業施設は制限
結果:適度な利便性と住環境のバランス
購入時の判断:
駅近の土地を検討。
近隣商業地域は「高層ビルが建つリスク」があると判断。
第一種中高層住居専用地域を選択。
「中高層マンションは建つが、大型商業施設は建たない」と確認。
5年後の現実:
予想通り、周りにマンションが数棟建った。
でも、高さは5〜7階建て程度。
大型商業施設は建たず、住環境は維持。
駅近で便利、かつ住みやすい。
木村さんの成功の秘訣:
「用途地域から『将来何が建つか』を予測しました。近隣商業地域なら10階建て以上も建ちますが、第一種中高層住居専用地域なら、中規模のマンション程度。バランスが良い選択でした」
成功の理由:
- 用途地域から将来を予測した
- リスクとメリットを天秤にかけた
- 「絶対に変わらない」を求めすぎなかった
- 現実的な判断をした
ケース4:市街化区域を選んで資産価値を維持(伊藤家・夫婦2人)
購入した土地:市街化区域(第一種住居地域)
特徴:インフラ整備、再建築可
結果:資産価値が維持され、将来も安心
購入時の判断:
格安の土地(市街化調整区域)と、やや高い土地(市街化区域)で迷った。
「市街化区域」を選択。
「将来建て替えできる」「資産価値が維持される」ことを重視。
10年後の現実:
建て替えも売却も自由。
インフラ(上下水道、ガス)も整備。
資産価値が維持され、売却時も高値で売れた。
伊藤さんの成功の秘訣:
「『市街化区域』と『市街化調整区域』の違いを理解していました。市街化調整区域は安いですが、再建築できない、インフラが整っていない、資産価値が低いなどのデメリットが多い。市街化区域を選んで正解でした」
成功の理由:
- 市街化区域と調整区域の違いを理解
- 長期的な資産価値を重視
- 「安い」だけで判断しなかった
- 将来の建て替えを考慮した
用途地域とは?13種類の特徴を理解しよう

用途地域とは、「その土地にどんな建物を建てられるか」を定めた地域区分です。
都市計画法によって、全国の市街化区域が13種類の用途地域に分けられています。
住居系(8種類)
特徴:最も住環境が守られる地域
建てられるもの:低層住宅、小規模店舗(50㎡以下)、学校
建てられないもの:中高層建物、店舗、事務所
高さ制限:10mまたは12m(2〜3階建て)
メリット:静か、日当たり良好、環境が変わらない
デメリット:店舗が少なく不便、土地が高い
おすすめ:子育て世帯、静かな環境を求める人
特徴:第一種より少し緩い
建てられるもの:低層住宅、150㎡以下の店舗
高さ制限:10mまたは12m
メリット:第一種より利便性がやや高い
デメリット:小規模店舗が建つ可能性
特徴:中高層マンションが建てられる
建てられるもの:住宅、マンション、病院、大学
建てられないもの:大型店舗、事務所ビル
高さ制限:なし(ただし日影規制あり)
メリット:駅近が多い、利便性が高い
デメリット:マンションが建つと日当たりが悪化
おすすめ:利便性重視、駅近希望
特徴:中高層マンション+1,500㎡以下の店舗
建てられるもの:住宅、マンション、中規模店舗
メリット:第一種より利便性が高い
デメリット:店舗が建つ可能性
特徴:住宅と商業施設が混在
建てられるもの:住宅、3,000㎡以下の店舗、ホテル
建てられないもの:パチンコ、カラオケ、工場
メリット:利便性が高い
デメリット:商業施設が建つ、騒音の可能性
おすすめ:利便性と住環境のバランス重視
特徴:第一種より商業色が強い
建てられるもの:住宅、大型店舗、パチンコ、カラオケ
メリット:非常に利便性が高い
デメリット:騒音、住環境が悪化する可能性
特徴:幹線道路沿いに多い
建てられるもの:住宅、店舗、自動車関連施設
メリット:店舗併用住宅が建てられる
デメリット:幹線道路沿いは騒音が大きい
おすすめ:店舗併用住宅を建てたい人
特徴:農地と住宅が共存
建てられるもの:低層住宅、農業関連施設
メリット:のどかな環境
デメリット:不便、農作業の音や臭い
商業系(2種類)
特徴:駅周辺に多い
建てられるもの:ほぼ全ての建物(工場除く)
高さ制限:なし
メリット:非常に便利
デメリット:高層ビルが建つ、騒がしい
注意:住宅地としては不向き
特徴:繁華街、オフィス街
建てられるもの:ほぼ全ての建物
高さ制限:なし
メリット:最も便利
デメリット:住環境としては最悪
注意:住宅地としては避けるべき
工業系(3種類)
特徴:工場と住宅が混在
建てられるもの:住宅、工場、店舗
メリット:土地が安い
デメリット:工場の騒音・振動、住環境が悪い
注意:住宅地としては避けるべき
特徴:工場専用
建てられるもの:工場、倉庫(住宅も建てられる)
建てられないもの:学校、病院、ホテル
注意:住宅地としては絶対に避けるべき
特徴:工業専用
建てられるもの:工場、倉庫
建てられないもの:住宅、学校、病院
注意:そもそも住宅が建てられない
土地選びで失敗しない7つのチェックポイント


用途地域を理解したら、次は実際の土地選びで確認すべきポイントです。
チェック1:用途地域を必ず確認する
確認方法:
- 市区町村の都市計画課で確認(窓口または電話)
- 市区町村のWebサイトで「都市計画図」を閲覧
- 不動産屋に「用途地域は?」と質問
- 重要事項説明書で確認(契約前に必ず確認)
用途地域は土地選びの最重要項目。必ず確認を。
チェック2:建築制限を確認する
用途地域が分かったら、次は具体的な制限を確認。
確認すべき制限:
- 建ぺい率(土地に対する建物の面積の割合)
- 容積率(土地に対する建物の延床面積の割合)
- 高さ制限
- 用途制限(何が建てられるか)
- 日影規制
チェック3:周辺の空き地を確認する
空き地は「将来何が建つか分からない」リスクがあります。
確認方法:
- 周辺に大きな空き地がないか
- 隣地が空き地の場合、用途地域を確認
- 「この空き地、何が建つ予定ですか?」と不動産屋に質問
- 近隣住民に「あの空き地、何か建つ予定ありますか?」と聞く
南側に空き地がある場合は特に注意。
チェック4:市街化区域か市街化調整区域かを確認する
市街化調整区域は、原則として建物を建てられません。
市街化調整区域:原則建築不可、再建築不可、インフラなし
非線引き区域:どちらでもない(地方都市に多い)
格安の土地は、市街化調整区域の可能性あり。必ず確認を。
チェック5:将来の開発計画を確認する
市区町村の都市計画を確認すれば、将来の開発計画が分かります。
確認すべきこと:
- 幹線道路の建設予定
- 駅の新設・移転計画
- 大型商業施設の建設予定
- 再開発計画
「将来幹線道路が目の前を通る」などが分かれば、避けられます。
チェック6:設計士に相談してから購入する
「この土地で希望の家が建つか」を、購入前に確認すべきです。
設計士に確認すべきこと:
- 希望の間取りが建つか
- 希望の高さ(3階建てなど)が可能か
- 店舗併用住宅が建てられるか
- 建ぺい率・容積率で問題ないか
土地を買ってから「建てられない」と分かっても手遅れです。
チェック7:複数の土地を比較する
1つの土地だけ見て決めるのは危険です。
比較すべきポイント:
- 用途地域
- 建築制限
- 周辺環境
- 価格
- 将来性
最低3つの土地を比較してから決めましょう。
用途地域の調べ方:5つの方法

用途地域は、以下の5つの方法で調べられます。
方法1:市区町村の都市計画課で確認する(最も確実)
手順:
- 市区町村役場の「都市計画課」に行く
- 「この住所の用途地域を教えてください」と質問
- 都市計画図を見せてもらえる
メリット:最も正確、建築制限も詳しく教えてもらえる
デメリット:役場に行く手間
方法2:市区町村のWebサイトで確認する
多くの市区町村が、Webサイトで都市計画図を公開しています。
検索キーワード:「〇〇市 都市計画図」「〇〇市 用途地域」
メリット:自宅で確認できる
デメリット:市区町村によっては非公開
方法3:不動産屋に質問する
不動産屋は用途地域を把握しています。
質問:「この土地の用途地域は何ですか?」
「建ぺい率・容積率は?」
「高さ制限は?」
メリット:簡単
デメリット:不動産屋が間違えることもある
方法4:重要事項説明書で確認する(契約前)
不動産売買契約の前に、必ず「重要事項説明書」が渡されます。
記載内容:
用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、その他の制限
契約前に必ず確認し、疑問があれば質問を。
方法5:オンラインサービスで確認する
「用途地域マップ」などのオンラインサービスもあります。
例:
・マピオンの「都市計画情報」
・各市区町村のGISシステム
メリット:手軽
デメリット:情報が古い場合あり
土地選びで迷ったら、プロに相談しよう
「用途地域、よく分からない…」
「この土地で大丈夫か不安…」
そう思ったら、一人で判断せずにプロに相談しましょう。
家づくり相談所
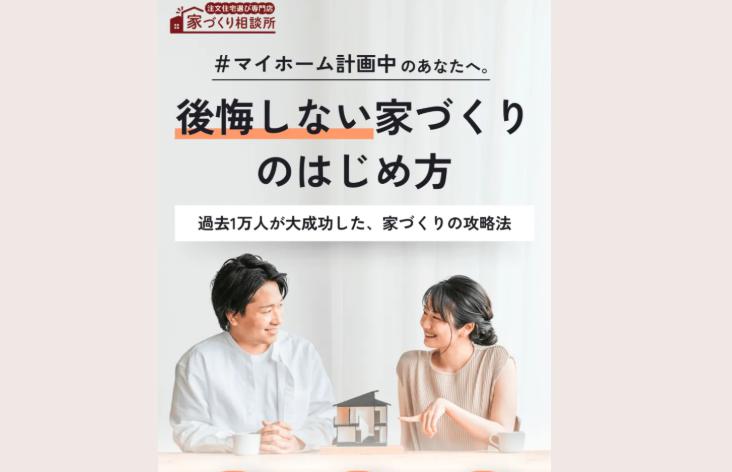
- 用途地域がよく分からない
- この土地で大丈夫か不安
- 将来何が建つか心配
- プロの目でチェックしてほしい
- 土地を買う前に相談したい
サービス内容:
- 初回相談無料(60分)
- 用途地域・建築制限のチェック
- 周辺環境の調査
- 将来のリスク分析
- 土地購入のアドバイス
相談者の声:
「格安の土地を見つけて飛びつきそうでしたが、プロに相談したら『市街化調整区域なので再建築不可』と指摘されました。相談していなければ、大失敗するところでした」(36歳男性)
希望に合った土地を複数社から提案してもらおう
用途地域を理解したら、希望に合った土地を探しましょう。
複数の不動産会社から土地を提案してもらうことで、最適な土地が見つかります。
タウンライフ家づくり

- 用途地域を考慮した土地を探したい
- 静かな住環境の土地が欲しい
- 店舗併用住宅が建てられる土地を探している
- 複数の土地を比較したい
- 土地探しに時間がない
サービス内容:
- 完全無料で利用可能
- 複数社から土地提案・間取りプランが届く
- 用途地域を考慮した提案
- 資金計画の提案
- 全国1,180社以上のハウスメーカー・不動産会社が対応
利用者の声:
「『第一種低層住居専用地域希望』と伝えたら、複数社から条件に合った土地が提案されました。用途地域を理解してくれる不動産会社を見つけられました」(34歳女性)
よくある質問(Q&A)
まとめ:用途地域は土地選びの最重要項目。必ず調べよう
用途地域を知らずに土地を買うことは、本当に危険です。
でも、用途地域を理解して土地を選べば、失敗は防げます。
この記事でお伝えした重要なポイントをおさらいしましょう:
- 用途地域を必ず確認する
土地選びの最重要項目 - 建築制限を確認する
建ぺい率、容積率、高さ制限 - 周辺の空き地を確認する
将来何が建つか - 市街化区域か調整区域かを確認する
再建築の可否 - 将来の開発計画を確認する
幹線道路、駅の計画 - 設計士に相談してから購入する
希望の家が建つか - 複数の土地を比較する
1つだけで決めない
用途地域は「将来何が建つか」を予測する重要な情報です。
「今の状態」だけで判断せず、「将来どうなるか」を考えましょう。
特に、以下の用途地域は住宅地としては避けるべきです:
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 市街化調整区域
逆に、以下の用途地域は住宅地としておすすめです:
- 第一種低層住居専用地域(最もおすすめ)
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域(駅近希望なら)
- 第一種住居地域(利便性重視なら)
用途地域を調べるのは、お金もかからず、手間もかかりません。
でも、調べないと大きな後悔につながります。
迷ったら、プロに相談してください。
あなたが用途地域で失敗せず、理想の土地に出会えることを心から願っています。
※プロが用途地域・建築制限を調査し、リスクを診断します
※用途地域を考慮した土地提案が複数社から届きます